-
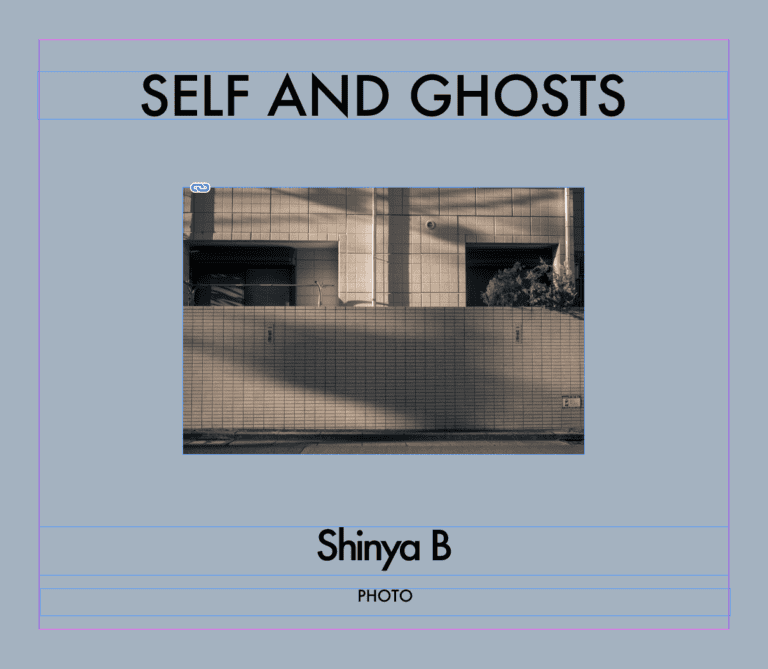 ブログ
ブログ
シンヤB写真展覧会のお知らせ / 2025年5月
-
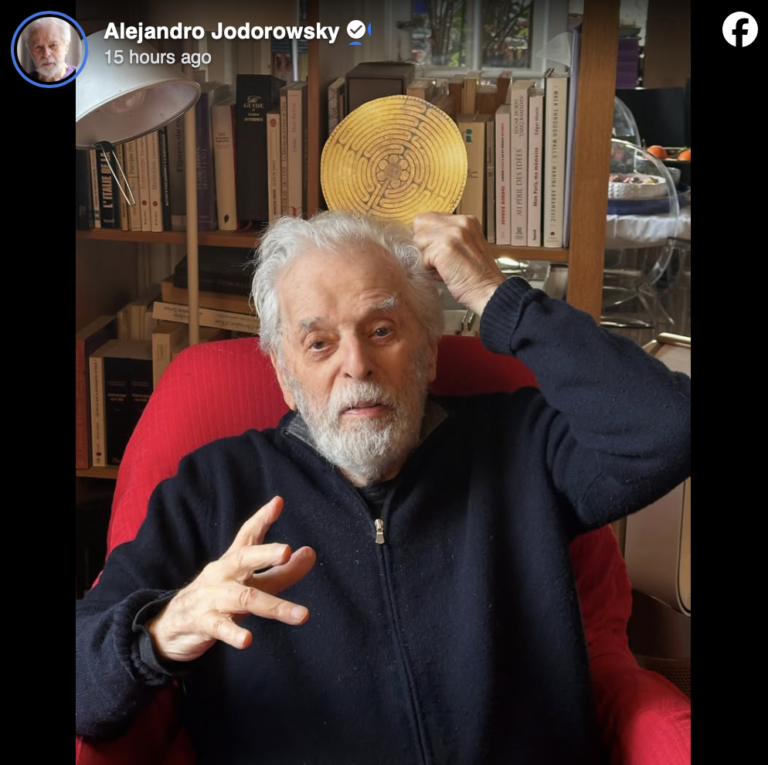 ブログ
ブログ
アレハンドロ・ホドロフスキーさん(映画監督で詩人)からの1月12日(日曜)のメッセージ
-
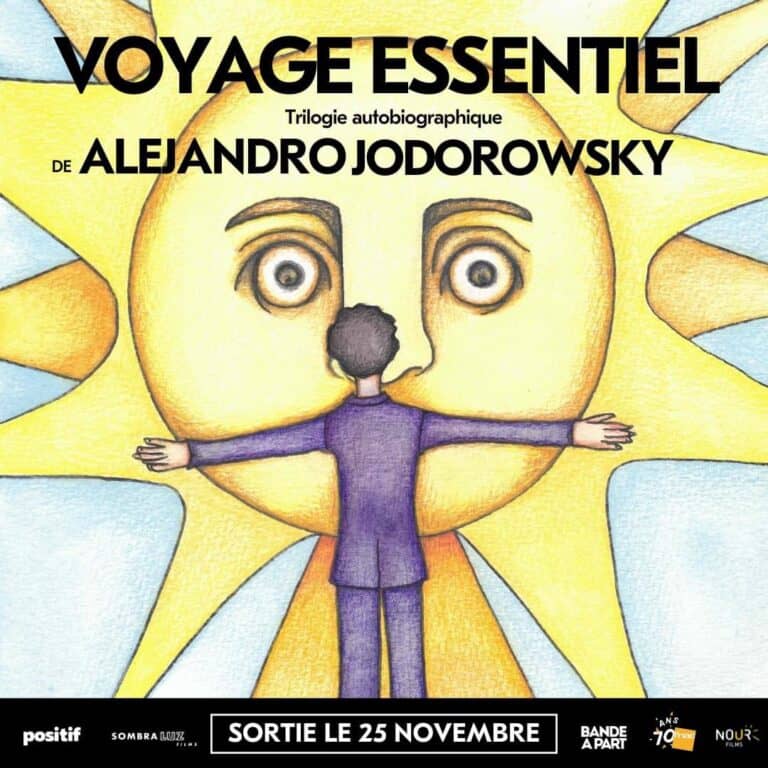 ブログ
ブログ
アレハンドロ・ホドロフスキーさん(映画監督で詩人)からの新年のメッセージ
-
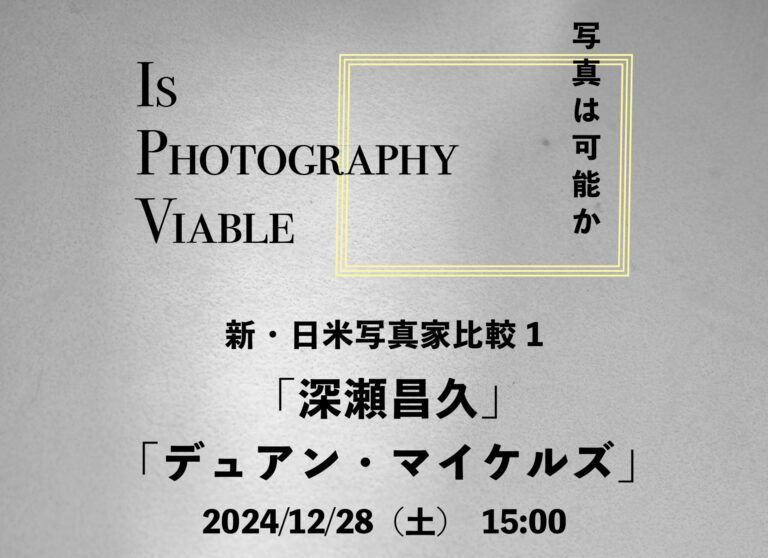 ブログ
ブログ
深瀬昌久 vs デュアン・マイケルズ — 写真は可能か 新・日米写真家比較
-
 雨の書
雨の書
16人の夏休み中の高校生と写真のワークショップを行ったので、少し書いてみる
-
 ブログ
ブログ
Human Baltic 展:写真に潜むダブル・スピーク(二重表現)パネルディスカッションの感想ノート
-
 雨の書
雨の書
軽井沢フォトフェス:「組写真のすすめ」 講義ノート
-
 ブログ
ブログ
写真は可能か — ダイアン・アーバスと森山大道
-
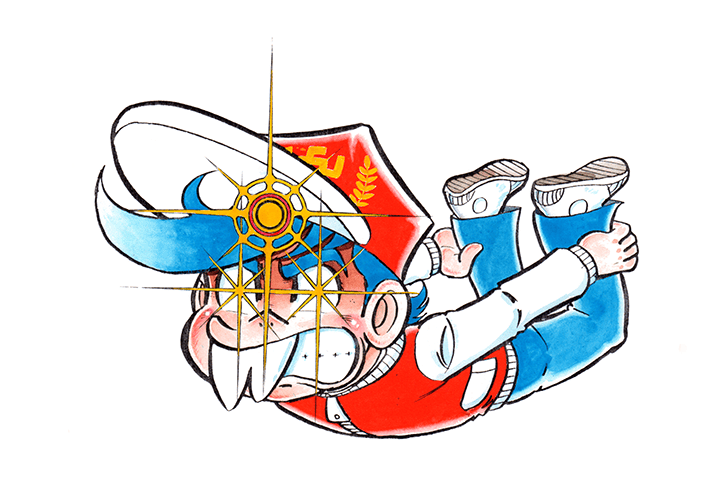 ブログ
ブログ
「ただし、学習されることに対する気持ちの部分と、収益が得られない経済面の部分については、切り離して議論した方がいいとも思います」– すがやみつるさん
-
 ブログ
ブログ
写真は可能か — アンセル・アダムスと土門拳
-
 書の書
書の書
書の書 Sunday, March 3, 2024
-
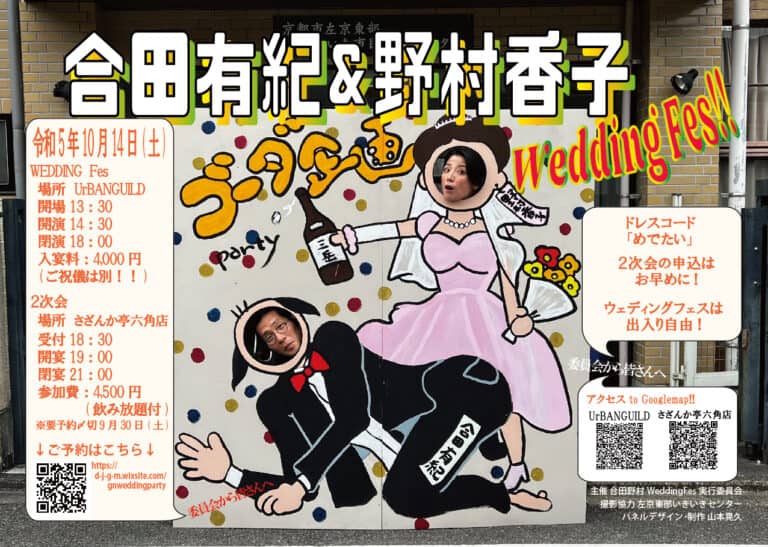 書の書
書の書
書の書 Kyoto